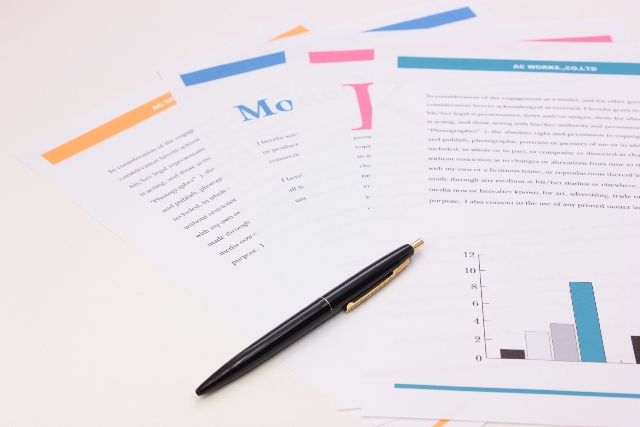


失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。
特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。
上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。
よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。
上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。
よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
失業保険 職業訓練を受講した場合の給付金等についていくつか質問させてください。
今月末に自己都合にて退職します。
調べてみたものの、よくわからないので詳しい方がおられましたら教えてください。
7月31日付退社予定。
年齢43歳。雇用保険期間17年。
7月の給料は0円なのですが、8月に支給される給料は有給休暇消費分(10日間)です。
6月の給料までの半年間の収入は、おおよそで115万円です。
9月から開催される、ハローワーク支援の職業訓練校にて3か月間受講予定です。
(詳細、手続きの仕方などはハローワークにて確認済みです)
そこで、1カ月当たり生活費として14万円は必要なのですが、
給付される失業保険のみで生活出来れば良いのですが、足りない場合アルバイトをしなければと思っています。
○1カ月当たりの給付金はいくら程度なのか?
○訓練校に通いながらアルバイトをした場合、どの程度の収入まで出来るのか?
○8月にアルバイトを予定してますが、不都合がありますか?
詳しい方おられましたら、どうぞよろしく御回答お願い致します。
今月末に自己都合にて退職します。
調べてみたものの、よくわからないので詳しい方がおられましたら教えてください。
7月31日付退社予定。
年齢43歳。雇用保険期間17年。
7月の給料は0円なのですが、8月に支給される給料は有給休暇消費分(10日間)です。
6月の給料までの半年間の収入は、おおよそで115万円です。
9月から開催される、ハローワーク支援の職業訓練校にて3か月間受講予定です。
(詳細、手続きの仕方などはハローワークにて確認済みです)
そこで、1カ月当たり生活費として14万円は必要なのですが、
給付される失業保険のみで生活出来れば良いのですが、足りない場合アルバイトをしなければと思っています。
○1カ月当たりの給付金はいくら程度なのか?
○訓練校に通いながらアルバイトをした場合、どの程度の収入まで出来るのか?
○8月にアルバイトを予定してますが、不都合がありますか?
詳しい方おられましたら、どうぞよろしく御回答お願い致します。
ざっくり計算すると凡そ12万円強くらいになると思います。
大体失業保険でもらえるのは6割~8割りくらいなので12万~13万の間になると思いますよ。
補足について
給付金の日額とアルバイト収入で得られる日額が在職中の1日当りの金額の80%を超えない範囲であれば減額されません。
仮に1月総支給額15万の給料であった場合 15万円÷30日=5000円 同じ様に給付額とアルバイトの給料(総支給額)を足して30日で割りその金額が5000円の80%の4000円以内であれば減額されません。
あとアルバイトについては注意点として2週間以上同じ職場でのアルバイトが続くと再就職したとみなされ受給資格がなくなりますのでご注意ください。
大体失業保険でもらえるのは6割~8割りくらいなので12万~13万の間になると思いますよ。
補足について
給付金の日額とアルバイト収入で得られる日額が在職中の1日当りの金額の80%を超えない範囲であれば減額されません。
仮に1月総支給額15万の給料であった場合 15万円÷30日=5000円 同じ様に給付額とアルバイトの給料(総支給額)を足して30日で割りその金額が5000円の80%の4000円以内であれば減額されません。
あとアルバイトについては注意点として2週間以上同じ職場でのアルバイトが続くと再就職したとみなされ受給資格がなくなりますのでご注意ください。
母親の失業保険のことでアドバイスお願いします。
10月末日で自己都合退職、離職時62歳、パートで8年勤務、雇用保険は入社時より加入しています。
支給額は平均8万前後、11日以上の勤務はあるのですが、今年の2月だけ5日しか勤務していないそうです(仕事による体調不良)
この場合は支給対象にはならないのでしょうか。
また、年齢的に再雇用が非常に厳しいと思いますが、ハローワークで職業検索をしたくらいでは仕事を探したにはあてはまりませんか?
10月末日で自己都合退職、離職時62歳、パートで8年勤務、雇用保険は入社時より加入しています。
支給額は平均8万前後、11日以上の勤務はあるのですが、今年の2月だけ5日しか勤務していないそうです(仕事による体調不良)
この場合は支給対象にはならないのでしょうか。
また、年齢的に再雇用が非常に厳しいと思いますが、ハローワークで職業検索をしたくらいでは仕事を探したにはあてはまりませんか?
8年近くお勤めであり、そのうち2月だけ体調不良で勤務日数が少なかったのですね。
その場合は、月に11日以上勤務していない月の分は見ませんから影響ありませんよ。
この質問だけで断定はできませんが、多分手続きは大丈夫ではないでしょうか。
(ただし、ドクターストップがかかっていたり本人に就職する意思がない等の場合はその限りではありませんが)
仕事探しに関してですが、ほとんどの安定所が安定所の検索機で探しただけで就職活動とみているようですが、そうでない安定所もあり、手続きされる安定所に直接聞かれた方がよいでしょうね。
その場合は、窓口相談やセミナー等が求職活動に入りますから、上手に活用してください。
ご参考になさってくださいね。
その場合は、月に11日以上勤務していない月の分は見ませんから影響ありませんよ。
この質問だけで断定はできませんが、多分手続きは大丈夫ではないでしょうか。
(ただし、ドクターストップがかかっていたり本人に就職する意思がない等の場合はその限りではありませんが)
仕事探しに関してですが、ほとんどの安定所が安定所の検索機で探しただけで就職活動とみているようですが、そうでない安定所もあり、手続きされる安定所に直接聞かれた方がよいでしょうね。
その場合は、窓口相談やセミナー等が求職活動に入りますから、上手に活用してください。
ご参考になさってくださいね。
失業保険について
1/31付でA社退職、有給消化中の1/25から派遣で二週間の短期勤務開始。
当初は二月上旬勤務終了予定も延長の繰り返しで退職したのが3/31。
短期契約の派遣では雇用保険加入
なし。
この状況で正直に申告したら、失業保険は認定されるでしょうか?
もし、約2ヶ月派遣で働いたことが不利になり、失業保険が認定されないのなら遠いハロワまで申請に行かないので、失業保険について詳しい方、教えてください!
ちなみに初めて失業保険を申請するため、右も左も分からないです。
1/31付でA社退職、有給消化中の1/25から派遣で二週間の短期勤務開始。
当初は二月上旬勤務終了予定も延長の繰り返しで退職したのが3/31。
短期契約の派遣では雇用保険加入
なし。
この状況で正直に申告したら、失業保険は認定されるでしょうか?
もし、約2ヶ月派遣で働いたことが不利になり、失業保険が認定されないのなら遠いハロワまで申請に行かないので、失業保険について詳しい方、教えてください!
ちなみに初めて失業保険を申請するため、右も左も分からないです。
A社の離職票はありますか?
離職票がなければ手続きはできません、また受給資格を得られるだけの被保険者期間はあるのでしょうか?
自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間が必要です。
被保険者期間があり、離職票があるなら受給手続きはできます、2ヶ月間働いていた事は問題ありません。
【補足】
待期と給付制限期間は違いますよ。
待期とは受給手続き日から7日間は完全失業状態を求められます、その間に働いた日があればその分待期が延びます。
キッチリ正しく申告した方がいいですよ、あとになって働いた事が発覚すれば不正受給と言う事になってしまい罰則を受ける事にもなります。
離職票がなければ手続きはできません、また受給資格を得られるだけの被保険者期間はあるのでしょうか?
自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間が必要です。
被保険者期間があり、離職票があるなら受給手続きはできます、2ヶ月間働いていた事は問題ありません。
【補足】
待期と給付制限期間は違いますよ。
待期とは受給手続き日から7日間は完全失業状態を求められます、その間に働いた日があればその分待期が延びます。
キッチリ正しく申告した方がいいですよ、あとになって働いた事が発覚すれば不正受給と言う事になってしまい罰則を受ける事にもなります。
契約社員で5ヶ月間勤務なのですが(延長なし)、失業保険は貰えるのでしょうか?
現在臨時雇用対策の求人にて、5ヶ月間契約社員として働いています。1日7時間で週5日の労働契約なので1ヶ月約20日勤務になります。月平均約17万円の総額で、5ヶ月間雇用保険を支払うことになりますが、退職後雇用保険は支払えるのでしょうか?もし支給になるのであれば、申請してから何日後の支給なのか、また支給される期間は何ヶ月(例90日間)なのか教えていただけませんか?
現在臨時雇用対策の求人にて、5ヶ月間契約社員として働いています。1日7時間で週5日の労働契約なので1ヶ月約20日勤務になります。月平均約17万円の総額で、5ヶ月間雇用保険を支払うことになりますが、退職後雇用保険は支払えるのでしょうか?もし支給になるのであれば、申請してから何日後の支給なのか、また支給される期間は何ヶ月(例90日間)なのか教えていただけませんか?
2007年10月1日の離職者からは基本手当受給の要件が「2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月あること」に変更されたので、残念ながら受け取るのは困難かと…
再度計算しなおして、該当するか検討して見てください!
補足後
臨時雇用対策の求人でしたよね!
たぶん、職場の人事に状況を説明すれば延長は可能だと思いますが?
その方がめんどくささが無くて済みますよ!
再度計算しなおして、該当するか検討して見てください!
補足後
臨時雇用対策の求人でしたよね!
たぶん、職場の人事に状況を説明すれば延長は可能だと思いますが?
その方がめんどくささが無くて済みますよ!
育児休業給付金と失業保険の事と育児休業後の退職の場合の残りの有給休暇について教えてください!!
育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
育児休業給付金を1年6ヶ月分受給しました。
ですが、子供の預け先が見つからず退社することにしました。
その場合、有給休暇を消化できるのでしょうか??
受給した育児休業給付金は返還するのでしょうか??
それと、退社後はハローワークなどで失業手当て?を支給してもらえるのでしょうか??
お詳しい方、ご回答宜しくお願いします。
1)有給休暇は、労働義務のある日について取得することができるので、育児休業が終了して職場復帰すれば取得することができます。当然ですが、退職日後は取得できません。
2)正当に受給した育児休業給付金を返還する規定(返還義務)はありません。
3)あなたの場合は雇用保険の基本手当の受給要件を満たしていると考えられるので、離職後にハローワークに求職の申し込みをして失業の認定を受ければ受給できます。(受給できないという回答がありますが、これは誤りです。たしかに、無給の間は雇用保険料を払う必要はありませんが、雇用保険に加入していないことにはなりません。休業中であっても雇用保険の被保険者です)
ただし、育児に専念して職探しをしないのであれば、基本手当は受けられません。
【補足】
以下は、3)についての補足説明なので読み飛ばしてかまいません。
まず、基本手当を受けるためには、算定対象期間(原則として離職日以前の2年間)のうちに「被保険者期間(説明は割愛します)」が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上)あることが必要です。
そして、育児休業により1年半休業していた期間は算定対象期間に係わる受給要件の緩和措置(※注)が受けられますから、あなたの場合、算定対象期間は通常の2年に1年半が加算された3年半になります。(ただし、育児休業していた期間は、所定給付日数の決定に用いられる算定基礎期間からは除外されます)
次に、育児休業給付金は「みなし被保険者期間(説明は割愛します)」が12ヶ月以上なければ受けられないので、現にこれを受給しているということは、結果的にあなたは「被保険者期間」に相当する期間が12ヶ月以上あることになります。
以上のことをまとめると、職場復帰後すぐに退職した場合、離職日以前3年半のうちに「被保険者期間」が12ヶ月以上あることになるので、あなたは基本手当の受給要件を満たしていることになります。
※注 行政手引50152(受給要件の緩和が認められる理由)の「ヘ」より引用
> なお、次の場合は、イからホまでに掲げる理由に準ずる理由として取り扱う。
(中略)
> (ホ) 育児
> この場合の育児とは、3歳未満の子の育児とする。
2)正当に受給した育児休業給付金を返還する規定(返還義務)はありません。
3)あなたの場合は雇用保険の基本手当の受給要件を満たしていると考えられるので、離職後にハローワークに求職の申し込みをして失業の認定を受ければ受給できます。(受給できないという回答がありますが、これは誤りです。たしかに、無給の間は雇用保険料を払う必要はありませんが、雇用保険に加入していないことにはなりません。休業中であっても雇用保険の被保険者です)
ただし、育児に専念して職探しをしないのであれば、基本手当は受けられません。
【補足】
以下は、3)についての補足説明なので読み飛ばしてかまいません。
まず、基本手当を受けるためには、算定対象期間(原則として離職日以前の2年間)のうちに「被保険者期間(説明は割愛します)」が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者又は特定理由離職者については6ヶ月以上)あることが必要です。
そして、育児休業により1年半休業していた期間は算定対象期間に係わる受給要件の緩和措置(※注)が受けられますから、あなたの場合、算定対象期間は通常の2年に1年半が加算された3年半になります。(ただし、育児休業していた期間は、所定給付日数の決定に用いられる算定基礎期間からは除外されます)
次に、育児休業給付金は「みなし被保険者期間(説明は割愛します)」が12ヶ月以上なければ受けられないので、現にこれを受給しているということは、結果的にあなたは「被保険者期間」に相当する期間が12ヶ月以上あることになります。
以上のことをまとめると、職場復帰後すぐに退職した場合、離職日以前3年半のうちに「被保険者期間」が12ヶ月以上あることになるので、あなたは基本手当の受給要件を満たしていることになります。
※注 行政手引50152(受給要件の緩和が認められる理由)の「ヘ」より引用
> なお、次の場合は、イからホまでに掲げる理由に準ずる理由として取り扱う。
(中略)
> (ホ) 育児
> この場合の育児とは、3歳未満の子の育児とする。
関連する情報